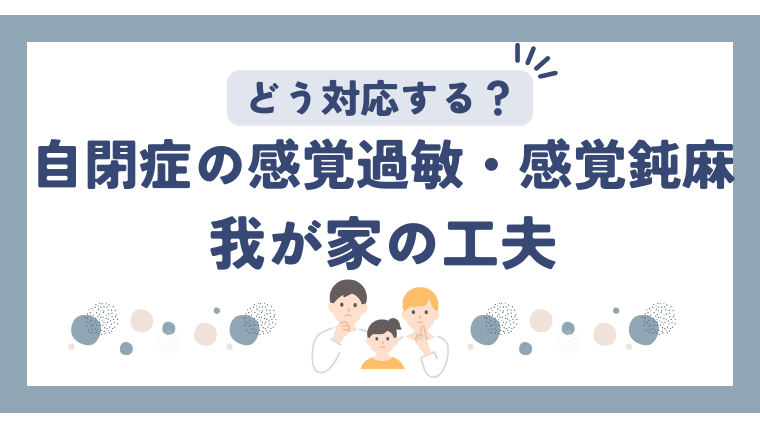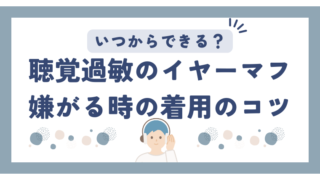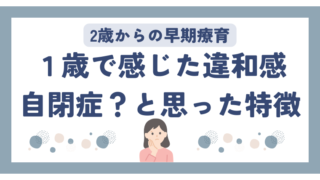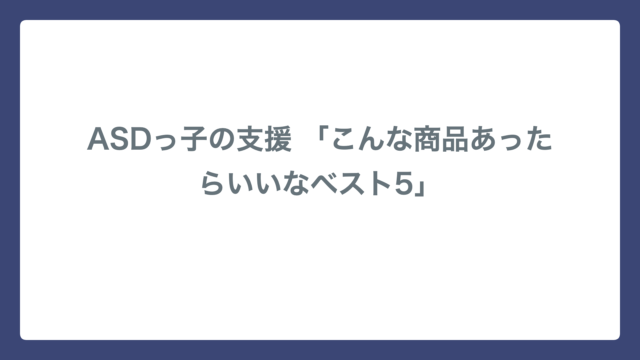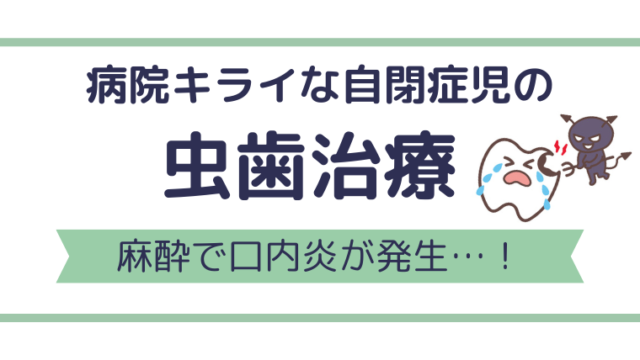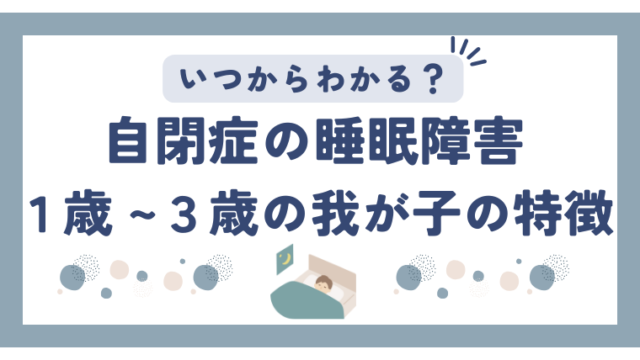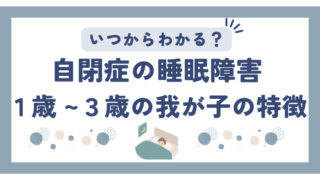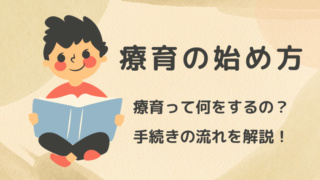でこぼこ長男は知的障害ありの重度の自閉症スペクトラムです。
そして、音や触れることに対してとても敏感な感覚過敏と痛みを感じにくい感覚鈍麻を併発しています。
コロナ禍のマスクの着用を嫌がったり、運動会の参加でパニックになるなど、一般的には困ることのない社会活動や社会生活の中で、理解してもらえず「生きづらさ」を感じてしまう感覚過敏。
そんな「感覚過敏」「感覚鈍麻」の特徴や長男の症状、我が家の対応についてご紹介します。
これは我が家の経験であり、医療的な助言ではありません。
感覚過敏とは?
感覚過敏について、「LITALICO|感覚過敏とは?チェックリストはある?原因や対策、発達障害との関連性も解説します【専門家監修】」にて、以下のように説明されています。
「感覚過敏」とは特性を表す言葉であり、病名ではありません。
感覚過敏とは、その名の通り聴覚や視覚、触覚などの感覚が過敏になっている状態を言います。
たいていの人は、何かが軽く触れたり、突然音が聞こえたりしたときに一瞬注意を払いますが、あまり気に留めることはありません。
しかし、感覚過敏がある人はたいていの人なら無視できるような状況や刺激を無視できなかったり、過敏に反応したりすることがあります。
そのため、感覚過敏があると日常生活や園、学校などの社会生活で困難が生じることが多くなります。
そして、感覚過敏の種類ですが、大きく6つあると言われています。
- 聴覚過敏
- 視覚過敏
- 味覚過敏
- 嗅覚過敏
- 触覚過敏
- 動きやバランスに関する過敏(前庭感覚の過敏)
これらの五感が敏感になっている状態です。
長男の感覚過敏は、年齢を重ねるにつれ、種類や症状に変化が出てきました。
長男の症状例
長男が持っているであろう感覚過敏の種類と症状については以下の通りです。
| 感覚過敏の種類 | 症状 | 具体例 |
| 触覚過敏 | 口元や頬の刺激に敏感 | ・マスクの着用ができない ・なんでもまずは口元に当てて確認する ・ヒンヤリとした肌触りの布団が好き ・歯磨き・爪切りが嫌い |
| 聴覚過敏 | 大きな音や高い音が苦手 | ・体育館で響く笛の音や太鼓の音が苦手 ・特定の子どもの泣き声が苦手 ・料理の音など生活音が苦手 |
| 視覚過敏 | 照明が眩しいところが苦手 | ・スーパーやコンビニに入ることができない ・夜の車のライトに敏感に反応する |
| 味覚、嗅覚過敏 | 見慣れないものを食べるときはまず臭う | ・同じ”切り干し大根”でも、家で作ったものしか食べず、惣菜は食べない ・ニオイを確認して嫌なものは絶対に食べない |
また、過敏さゆえに特定の音や映像を気に入って何度も見たり、くるくる回る、跳ねるなどの特定の感覚を好む「常同行動」も見られます。
スーパーは店内の音楽が鳴り響いていたり、照明が眩しいこともあり、慣れるまで時間がかかります。
今でも不安な気持ちが強い時は、入店拒否したり、抱っこで移動することもあります。
長男の場合、聴覚や視覚については、慣れてくるとあまり嫌がることはなくなりますが、触覚、味覚に関しては、なかなか慣れることができないようです。
感覚鈍麻とは?
一方で感覚鈍麻とは、特定の刺激に対する反応が低くなることで、痛みを感じにくかったり、暑さや寒さに気づかないことなどがあります。
●感覚鈍麻の原因について
感覚鈍麻の原因はあいまいではっきりとはわかっていませんが、感覚を伝達する際の神経信号の伝わり方の問題や信号を受け取ったあとの処理に原因があると考えられています。
引用:https://junior.litalico.jp/column/article/091/
長男の症状例
長男は、「痛みを感じにくい」です。
2歳ごろに、玄関の階段の少し高いところから落ちましたが、痛みよりその感覚が楽しかったようでニコニコしていました。
現在も気づいたら、体にアザや出血があったりします。
また、痛みに対しての感覚が鈍いために、虫歯が進行し、6歳の時に神経まで達している虫歯が7本発見されました。
感覚過敏と感覚鈍麻への対応「不安を軽減」
先ほど挙げてきたように、感覚過敏の症状として様々な種類があります。
過敏さゆえに、日常生活において、「やらないといけないのに、できないこと」があります。
感覚過敏や感覚鈍麻は、本人の感じ方の問題なので治すことが難しいです。
そして、感覚過敏への対策について、どの感覚に関しても共通して言えることがあります。それは、「不安を軽減する」ことです。
参考:https://junior.litalico.jp/column/article/016/
ここからは、我が家の対応方法について、紹介します。
聴覚過敏への対応
● 困りごと
- 歯磨きができない
- 爪切りができない
- 散髪ができない
触覚過敏があると、生活する中で身だしなみを整える部分が、本人にとってとても苦痛のようです。
対応方法「短い時間で終わらせる、毎日続けて慣れさせる」
幼いころは、子どもの両手を私の両足で押さえて歯磨きをしていましたが、身体が大きくなり難しくなりました。
必死に抵抗しており、「嫌なことをされる」という不安が大きいのでしょう。
現在は、サンスターの歯磨き動画を見せながら、座ってやるようにしています。
散髪もとても嫌がりますが、時間を短くして、家でやるようにしています。
合わせて読みたい関連記事
爪きりは、どうしてもできないようなので、寝た直後の深い睡眠の時にやっています。
聴覚過敏への対応
● 困りごと
- 料理の音など生活音が苦手で家でずっと耳ふさぎをしている
- スーパーのBGMが苦手で、スーパーに行くと座り込む
外出先、自宅において、様々な音が気になって、落ち着いて過ごせません。
対応方法「イヤーマフ」
7歳からイヤーマフを着用するようになり、以前より、家や外出先で落ち着いて過ごせるようになってきたように思えます。
味覚過敏への対応
● 困りごと
- 偏食で、給食や外食が食べれない
対応方法「給食で少しずつ慣れていく」
長男は就学し、給食でいろんな料理に触れるようになり、一口ずつですが、食べれるものが増えてきました。
ご飯(白米)は食べるので、ご飯の日はふりかけを持参して、食べるようにして、パンや麺類の日は白米を持参しています。
外食時は、食べれるお菓子やおかずを持参したり、食器を持参して、なるべくいつもの環境に近い状況を作るようにして、不安を軽減させるようにしています。
無理強いはせず、食に興味を持ってもらうことを第一に考えています。
長男は、コロナ禍に療育園で”マスク着用の練習”をしたり、運動会の笛の音に慣れるために、”療育の中で笛の音を少しずつ聞かせていきました”。
マスクは少しの間であれば着用できるようになりましたし、最後の運動会は嫌がることなく参加することができるようになりました。
大泣きだった初めての運動会、ずっと耳を塞いで泣いていました。少しかわいそうになったけど、最後の運動会をとても楽しそうに過ごしていて、成長を感じてとても嬉しかったです!
我が家では、学校やデイサービスと連携し合い、無理に治そうとせずに、慣れていくことを意識しています。
感覚鈍麻への対応
● 困りごと
- 虫歯が進行していても気づかない
対応方法「定期的に歯医者に行く」
5歳の時に、大きな虫歯が何本も見つかったことで歯科へ通院するようになりました。
歯磨きもちゃんとすることができず、痛みを訴えることもない長男。
そこからは、早めに虫歯や痛みに気付けるように、2か月に1回を目安に歯科検診に行くようにしています。
合わせて読みたい関連記事
まとめ
感覚過敏や感覚鈍麻は本人の感じ方の問題で、子どもの頃はその不快感をうまく伝えることができず、周りの理解や配慮がないと辛いと思います。
親としては、なるべく理解してあげたいですが、何が嫌なのか分からないことも多く付き合っていくのが難しいです。
社会で生活していく上で避けることができないことであれば、継続することで慣らしていくしか解決方法がありません。
生活する上で必要な嫌な感覚が減っていくことで、本人が「生きやすくなる」こと。
これが親である私が今できることではないかと感じています。