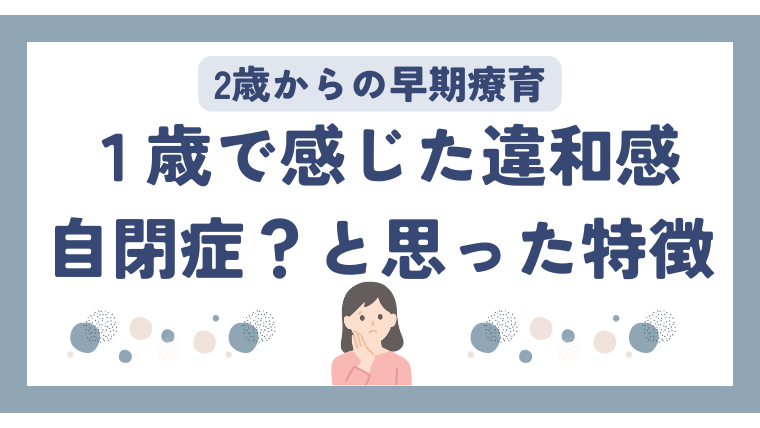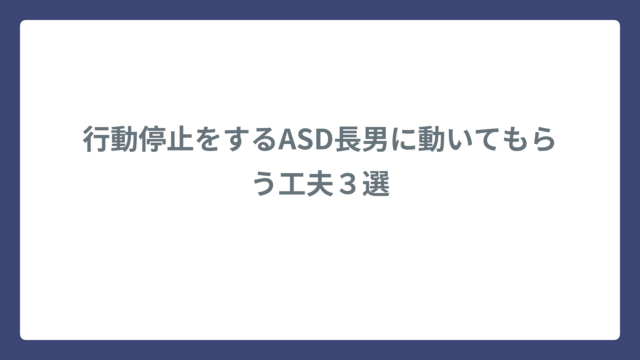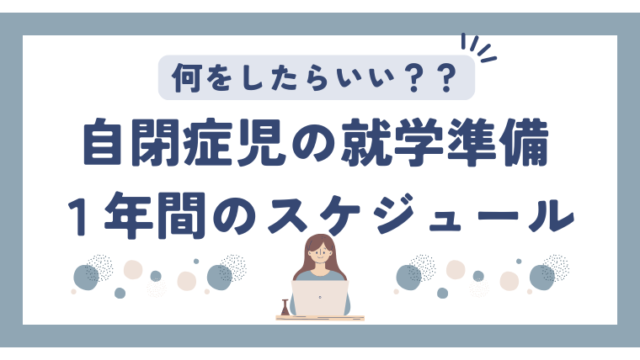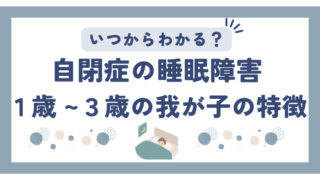でこぼこ長男は知的障害ありの重度の自閉症スペクトラムです。
1歳前後から、喋らない、指差しをしない、つま先歩き、真似をしない、手をつなぐことができない、など違和感を感じ、療育を始めることになりました。
発達障害は、それぞれ特性があり、ひとくくりで判断することが難しい障がいです。
この記事では、1歳から感じた長男の発達の違和感から療育をはじめるきっかけとなった1歳半健診について、ご紹介します。
この記事では以下のことが分かります。
- 0歳~3歳の自閉症の特徴と息子の特徴
- その他の特性・過敏性
- 相談・療育を始めるまでの経緯
これは我が家の経験であり、医療的な助言ではありません。
0歳~3歳の自閉症の特徴と息子の特徴
参考:『自閉スペクトラム症(ASD)の特徴とは??0〜6歳の年齢別に子どもの行動特性を紹介』(神戸医療福祉専門学校・https://www.kmw.ac.jp/contents/occupational-therapist/autism-spectrum-disorder )
参考:『自閉的傾向のある子どもに見られる特徴』(キッズハグ・https://kidshug.jp/check/check01/)
上記のサイトを参考に、一般的な幼少期の自閉症の特徴や症状に対して、診断前の長男にもよく見られた症状をチェックしました。
| 長男の症状 | 一般的な幼少期の自閉症の特徴 |
|---|---|
| ✔ | 視線が定まらない |
| ✔ | 抱っこをしようとすると身体を大きく反らす |
| 笑わない | |
| ✔ | 聞きなれない音に異常に反応 |
| ✔ | 人見知りがない |
| ✔ | 呼びかけや大きな音に無反応 |
| ✔ | けがをしても痛がらない |
| ✔ | 後追いをしない |
| ✔ | 指さしの方向をみない他者の視線を追わない |
| ✔ | 注意を引きたいときに、その人の手を直接ものに触れさせる(クレーン現象) |
| ✔ | 眠りが浅い、寝つきが悪く睡眠時間が安定しない |
| ✔ | つま先歩きをする |
| ✔ | 一つの遊びに没頭 |
| お気に入りの色以外のものを身につけるのを嫌がったり、遊びの順序のこだわりがある | |
| 動きのぎこちなさや、走る、跳ねるなどの全身運動が苦手 | |
| ✔ | 手をひらひらさせる、身体を揺らす、同じところをぐるぐる回るといった常同行動 |
| ✔ | 言葉の理解、言語発達の遅れ |
| オウム返し | |
| ✔ | 食べ物の好き嫌い |
| ✔ | ひとり遊びが好き、ごっこ遊びが苦手 |
| ✔ | 物の位置やいつも通りの場所にこだわる |
| お友達とけんか | |
| ✔ | 相手のためにする行動がない |
特に分かりやすく気になったのは、「つま先歩き」「呼びかけに反応しない」でした。
長男の場合、多くの自閉症の症状が該当していたこともあり、これらをきっかけに早めに療育を始めることになりました。
また、現在(6歳)に至るまで、上で挙げた特徴は今もほとんど見られます。
6年過ごして、改めて障害を治すのではなく、特性を理解し、付き合っていくということが大事なんだなと感じます
発達障害〜3歳以降での特徴や特性とは?
長男は重度の自閉症で、言葉の発達も遅く、1歳の時には違和感を感じていましたが、ASD(発達障害)は、3歳以降の健診で診断を受けることも多いようです。
長男の療育園でも、4歳ごろに入園するお子さんが多かったです
3歳の発達障害の子どもの特徴としては、以下が挙げられています。
参考:『LITALICO- 3歳の発達障害のある子どもの特徴は?』(LITALICO・https://junior.litalico.jp/column/article/106/)
- 言葉に遅れがある
- 周りの子どもと人間関係をうまく築けない
- 落ち着きがない
- 変化があると不安やパニックになる
- 癇癪を起すことが多い
- 視覚や聴覚など感覚敏感がある
併発していた合併症
長男の場合、合併症として、「睡眠障害」「多動症」「知的障害」があります。
どれも自閉スペクトラム症に併発しやすいと言われています。
参考:『自閉スペクトラム症に併存しやすい疾患・障害』(すまいるナビゲーター・https://www.smilenavigator.jp/asd/abc/04.html)
症状例
「睡眠障害」
乳児期は一般的な睡眠でした。
1歳前後から寝つきが悪くなり、1時まで起きていることもありました。
寝室へ行っても落ち着かず、ずっと動き回っていました。
現在はメラトベルを薬を服用して、入眠でいるようになりました。
参考:『薬物治療が必要とされる場合と使用される薬』(すまいるナビゲーター・https://www.smilenavigator.jp/asd/abc/05.html)
「多動症」
落ち着きがなく、長時間座っていることが難しいです。
療育を始めて、朝の会や帰りの会では着席して過ごすことができるようになりました。
「知的障害」
長男は、2歳で療育手帳Bを取得し、5歳で療育手帳Aに更新しました。
合わせて読みたい関連記事
相談・療育を始めるきっかけ【経験談】
これまで挙げてきた通り、長男の違和感は自閉スペクトラム症の症状に該当する部分が多くありました。
しかし、誰にどのように相談したらいいのか分からず、ただ一人で不安と疑いを抱えていました。
そんな私が、長男の発達に対する不安を最初に相談したのは、1歳半健診でした。

「何か違う」と感じながらも、初めての子で分からない。
1歳半健診で、詳しい人の意見を聞いてみようと思いました。
①1歳半健診で相談
1歳半健診とは?
1歳半健診では、運動機能や視聴覚など身体の成長と、精神発達の度合いをチェックします。それにより、お子さまの発達状況を把握するとともに、先天性疾患や精神発達の進度などの問題を早期発見し、適切に指導・対応することで心身障害の進行を防止することが目的です。
引用:ベネッセ教育情報 – 1歳半健診とは?
- 母子手帳への記入
- 身体測定
- 歯科健診&虫歯予防の指導
- 医師の診察
- 待ち時間の様子を見る
- 保健士と面談
私の住んでいる市の1歳半健診では、上記の内容について、医師や保健師が確認をしていきます。
長男の健診時の様子
✔ 母子手帳への記入
健診までに、母子手帳の「保護者の記録」欄に記入を行います。
長男の場合、この時点でできないことや迷う項目が多く、ますます不安に…。
✔ 歯科健診&虫歯予防の指導
歯科検診は、大暴れ。なんとか抑えて診察してもらいました。
長男は、虫歯予防の説明を聞くことなく、部屋の探索活動をしてました。
✔ 医師の診察
医師が名前を呼ぶが返事なし。むしろ逆方向へ走り出していました。
✔ 待ち時間の様子
部屋を動き回る、危ないところへも入っていくので待ち時間がとても大変でした。
✔ 保健士と面談
絵本の指差し、発語の確認、つみきの積み上げなどを行います。
長男の場合、「発語なしで、指差しはしていないけど、絵本で指をさした「モノ」を目で追っている」と言われました。
1歳半健診の結果
「まだ何とも言えない、2歳まで待ちましょう」 と判断されました。
保健士さんは、とてもプラスのアドバイスをしてくれますし、親身に相談にも乗ってくれますが、不安だらけの私には「ポジティブすぎないか・・?」と不安が少し残りました。
しかし、まずは相談できる窓口に繋がることができ、第一歩を踏み出しました。
②参観日での違和感
1歳半健診の1ヶ月後に、保育園の参観日がありました。
体育の先生を外部講師として呼び、マットや平均台を使い親子で身体を動かす内容でした。
参加日での長男は…
- マットへの興味が持続しない
- 手をつないで歩くことができない
- 待ち時間にそばを離れる&危ない場所へどんどん進む

他の子がお母さんと会話をしたり、コミュニケーションをとっている中、私から離れていく長男に途中で涙が出てきそうになりました。
家に帰り、涙が溢れてきました。
不安に押しつぶされそうになり、土曜日に開いている相談窓口を探し電話をしました。
エンゼル110番「育児に関する無料電話相談」に相談
エンゼル110番とは?
エンゼル110番は、森永乳業株式会社の委託を受けて株式会社森永乳業ビジネスサービスが運営する、妊娠中から小学校入学前までのお子様に関わる皆さまを対象とした無料の育児相談窓口
引用:エンゼル110番「育児に関する無料電話相談」
電話相談の相手は、管理栄養士や心理相談員など有資格者です。 未就学児までの子供について、子育てに関わる相談をすることができます。
相談内容について
参観日で感じたこと、1歳半検診で言われたこと、今の不安な気持ち、どうしたらいいかわからないことについて相談しました。
絶望感満載で取り乱す私に対して、落ち着かせるよう優しい口調で、色々なアドバイスをいただきました。

まずは、月曜日に保健士に電話してみませんか?
その間にできることとして、まずは夜間のミルクをやめてみましょうか?
③保健師へ相談
アドバイス通りに月曜日に保健所に電話し、後日、保健師さんが保育園に様子を見に来ることになりました。
その後、家の様子も見に来てもらい今後の方針について話をしました。
保健師さんから言われたこと

- 保育園では、ひとり遊びをしていることが多かった
- 療育は早い方がいいと言われている。
- お母さんが療育を希望するのであればすぐに手続きを進めることもできる
- 児童発達支援センターの発達支援相談窓口に先に相談することもできる
迷わず、「すぐに療育をしたいです!」と、答えました。
めかぶ 当時の私は、何か行動を起こしていないと、将来への不安に押しつぶされそうでした…。
そこから療育施設へ通うために、手続きなどを始めました。
合わせて読みたい関連記事
まとめ
最初に、何か違う???と感じたのは1歳5か月、保育園に入園したころです。
発語がないこと、指差しがないこと、つま先歩き、手をつなぐことができないこと、同年齢の子を見て、「あんなこともできるの?」と思うことが多かったのです。
直感で感じたことで、家族や先生、友人に相談しても、「男の子は発達が遅いから大丈夫!」と言われることが多く、何を言われても私が感じる不安は解消されませんでした。
3歳までは、医師でも確実な診断はできないということが多いのが現実ですが、不安なことがあるなら、保健師や専門家に相談してみることをオススメします。
一人で悩んで悶々としていた日々は、毎日不安で暗闇にいるような状況でしたが、相談したことで今何をしたらいいのか、方向性を示してもらうことができました。
家庭ごとに合う方法は違いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。