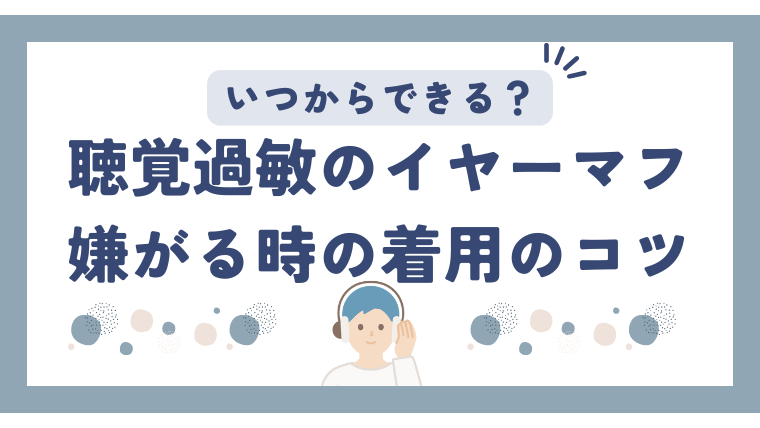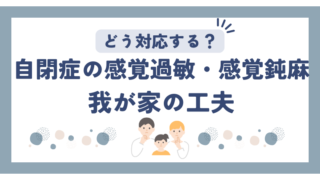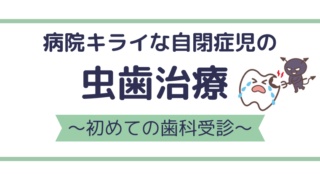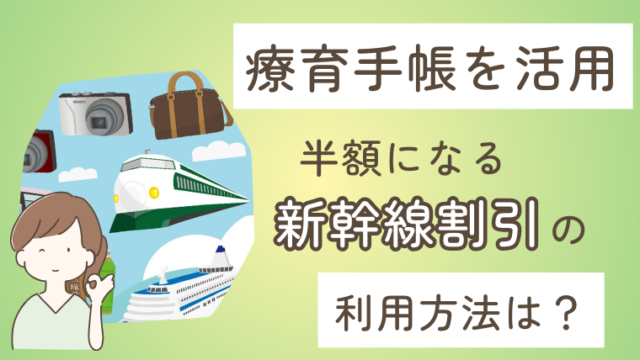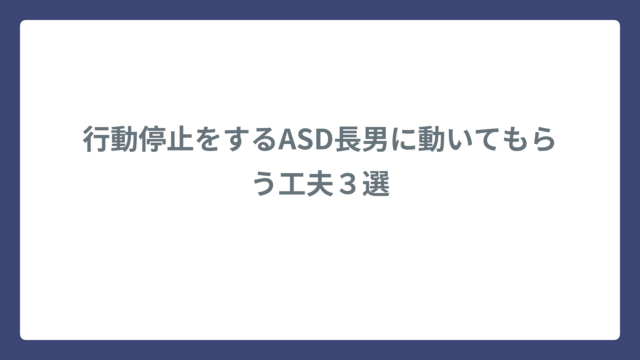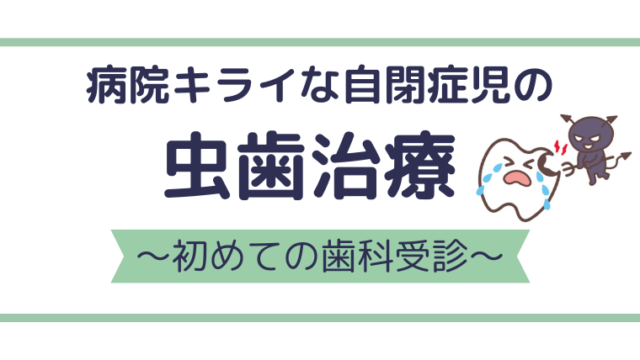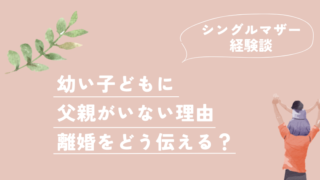でこぼこ兄弟の長男は重度の自閉症スペクトラム障害です。
2025年現在7歳の特別支援学校2年生です。
長男は「聴覚過敏」「感覚刺激」「視覚過敏」などの感覚過敏を持っており、私にとっては些細なことで混乱やパニックを起こします。
5歳のごろから、聴覚過敏で耳ふさぎを始めた長男ですが、触覚過敏もあり、防音対策の耳当てのイヤーマフをつけることができませんでした。
しかし、少しずつ慣れていくことにより、7歳になり、イヤーマフを着けることができるようになりました!
そんな感覚過敏だらけの長男が、イヤーマフがつけれるようになった時のことについてご紹介いたします!
※これは我が家の経験であり、医療的な助言ではありません
聴覚過敏とは
- 聴覚過敏
- 視覚過敏
- 味覚過敏
- 嗅覚過敏
- 触覚過敏
- 動きやバランスに関する過敏(前庭感覚の過敏)
聴覚過敏は、感覚過敏の一種で、突然の音や騒音などに対して過敏の状態を示すことです。
参考:https://junior.litalico.jp/column/article/016/
長男が特に苦手な音について
- 子供の泣き声や叫び声
- 食器を洗う音
- 料理の音(包丁・焼く音)
- 換気扇
- スーパーのBGM

成長するにつれて、どんどん苦手な音が増えて、5歳ごろから頻繁に耳ふさぎをするようになりました。
聴覚過敏の影響
苦手なものに挙げてきたように、5歳くらいから、家の中や外出先、学校で常に耳塞ぎをするようになりました。
食事中は生活音が気になり、落ち着いて食事をとることができません。
様々な要因で、過敏になっている時は、音をきっかけにパニックを起こすこともありました。
また、耳を塞ぐことで手を使うことができなくなるため、手を使う作業(手を洗うなど)がやりづらそうでした。
そこで、「イヤーマフ」の着用を検討しました。
聴覚過敏の対策「イヤーマフ」
イヤーマフは、周囲の不快な音を遮断することができます。
音が全く聞こえないわけではなく、聴覚過敏の人にとって生活しやすくなるアイテムです。
イヤーマフを装着できるようになるまで
イヤーマフを購入し、自宅で装着
年長の時に、イヤーマフを購入し、家でさっそく使ってみました。
3秒くらいは身につけることができましたが、すぐに嫌になってしまい外しました…
触覚過敏を持つ長男にとって、イヤーマフは耳を圧迫するので、痛みを感じるのか、違和感を感じているようでした。
その後も数回利用しましたが、すぐに嫌がるので一度断念しました。
ヘッドホンを購入し、YouTubeの動画を見せる
まずは耳に着けることになれてもらうために、圧迫の少ないヘッドホンを購入しました。
はじめは嫌がりましたが、好きなYouTube動画の音をがヘッドホンから出ているのを確認すると、嫌がることなく装着することができるようになりました。

ヘッドホンは、病院の待合室や外食など、静かにしないといけない時に利用しています。
放課後デイサービスでイヤーマフを装着
ヘッドフォンの装着に慣れたころに、放課後デイサービスより、提案がありました。
耳ふさぎを常にしているので、イヤーマフの練習をしたいのですが・・・
家よりも学校や放課後等デイサービスは、様々な音が聞こえていて、集中できず不快に感じているようでした。
もちろん承諾し、放課後等デイサービスに置いてあるイヤーマフの着用を毎日してもらいました。
はじめは、数秒で外していたようですが、イヤーマフをつけることで、不快な音が聞こえなくなることに気付いてからは、帰るまで装着できるようになりました。
デイで装着できるようになってから、自宅用に購入したイヤーマフを放課後等デイサービスに持って行くようにし、練習してもらいました。
長男は抵抗なく自分のイヤーマフをつけることができ、放課後等デイサービスからイヤーマフをつけたままバスで帰ってきて、家でも着用したまま食事をとることができるようになりました!!
触覚過敏でつけれなかったはずなのに・・・!先生すごい・・・(感動)
聴覚過敏の子どもにイヤーマフを取り入れるコツ
長男のように「言葉での意思疎通ができない」「触覚過敏もある」人の場合、いきなりイヤーマフを着けることは、嫌悪感を感じると思います。
そこで、放課後デイサービスの先生に教えてもらった聴覚過敏の人にイヤーマフを取り入れる時のコツは、以下の通りです。
①嫌な音がする状況で着用する
↓
②嫌な音が聞こえにくいのを体感する
↓
③少しずつ、つけている時間が長くなる
家ではなかなか取り組めないことでも、経験のある放課後等デイサービスで慣れさせてもらえたことで、使用できるようになりました。
長男がイヤーマフを取り付ける場面

- 家でipadをする
- 車や学校のバスに乗る時
- 買い物中
- 家で食事中
- 放課後等デイサービス
全く聞こえないわけでもなく、声掛けには反応して応じています。
現在は、長男から「イヤーマフをつけたい」とアピールしてくれたり、不要なときは自ら外すような行動が見られます。
イヤーマフ着用後の変化
イヤーマフをつけるまで様々な音が気になり、片耳や両耳を耳をふさいでいた長男。
現在は、自分の意思で、抵抗なくつけたり外したりするようになりました。
イヤーマフのメリット
両手で作業ができるようになった
食事や療育の間も耳を手でふさいでいたので、どうしても片手しか使えませんでしたが、両手を使って食事をとることができるようになりました。
食事に集中できるようになった
食事中に、食器の音や料理の音(フライパンで焼く音や揚げ物の音など)が気になっていたのですが、イヤーマフでその音が聞こえにくくなったようで、気にしないようになりました。
不安な気持ちを落ち着けるようになった
長男の耳ふさぎは、不安なときにもふさいでいるようなことがありました。
(祖父がそばからいなくなる時、バスに乗る時など)
不安からパニックが起きることもあるので、パニックが起きる前に不安な気持ちを落ち着かせるために、何か不安を感じそうな時には、事前にイヤーマフを取り付けるようにしています。
イヤーマフのデメリット
耳への圧迫が強く、蒸れやすい

長男は長い時で3時間くらいイヤーマフをつけていますが、外してみると耳の周りが赤くなっています。
さらに、写真のようにイヤーマフを少し上にずらしたりしているので、「痛いか暑い?」と、考えています。
これに関しては、様々なイヤーマフが販売されているので、イヤーマフの種類によるのかもしれません。
言葉で感想を伝えることができないので、本当のところはわかりませんが、つけることを嫌がりませんし外そうともしないので、落ち着けるのであないかなと思っています。
<疑問>イヤーマフは、歯医者で使えるのか?
まとめ
感覚過敏が強い長男にとって、生活の様々な音が嫌でそれが原因でパニックや不眠、癇癪が起きていました。
触覚過敏がある長男に「イヤーマフは無理だろうな」と考えていましたが、放課後等デイサービスの支援により、支援学校1年の冬(7歳)からつけることができるようになり、家族の支援もやりやすくなりました。
しかし、イヤーマフだけで予防することができないパニックもあります。
感覚過敏の長男にとって、私にはわからない生活のあらゆる場面で伝えられない辛さがあるのでしょう。
長男が穏やかに日常生活を過ごせるようになるために、今後も様々な便利グッズや長男の環境調整に取り組んでいきたいと思います!
家庭ごとに合う方法は違いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。
紹介した商品について
▲コンパクトにおさまり、持ち運びが楽です。イヤーマフ初心者のお子様に向いていると思います!
▲1回充電するだけで、長時間利用できるのでとても便利です。長男と次男で3歳〜7歳の時に使ってますが、サイズ感も問題なく使えました。