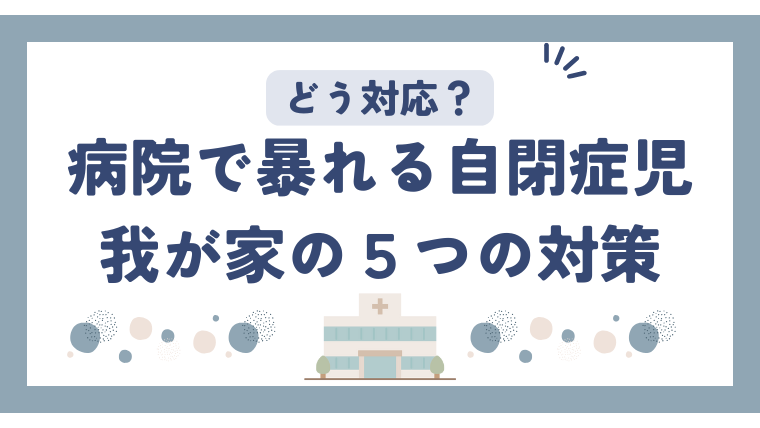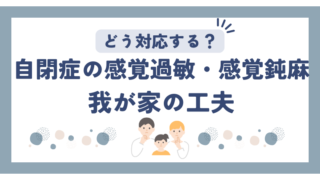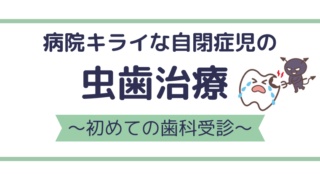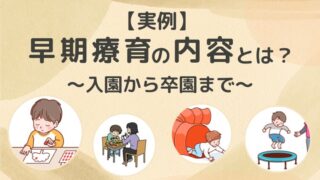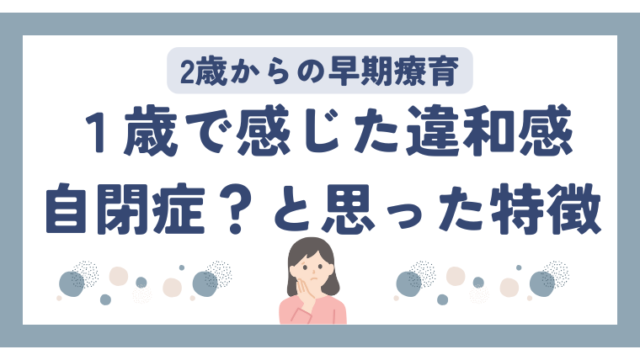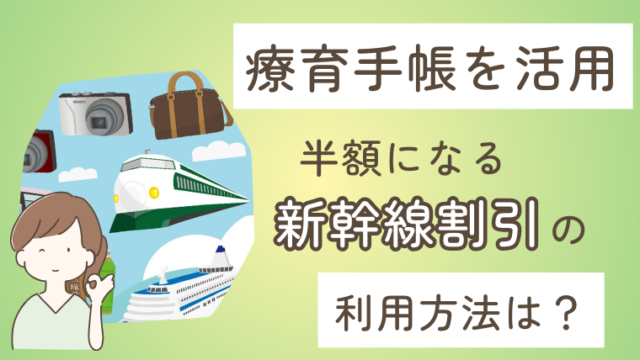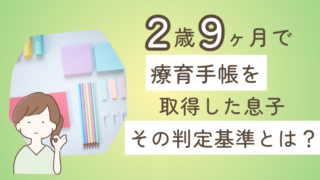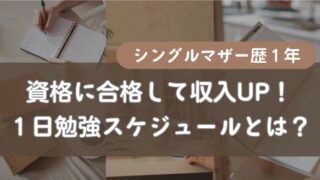でこぼこ兄弟の長男は知的障害ありの重度の自閉症スペクトラムです。
病院が怖くて嫌いな長男は、未就学児の頃は大泣き大暴れでした。
終わった時には、長男は汗だく、私は髪の毛ボサボサです。
長男の病院嫌いは、2歳ごろからはじまりました。
小さい頃は身体も小さいのでなんとかなりましたが、身体が大きくなった現在、病院に行くだけで親の方が少し老けた気分になるくらい疲労がすごいです。
発達障害のお子さんの中にも特に病院が苦手な人はとても多いようです。
そんな長男の病院嫌いに対しての先生や看護師さん、家族の戦いの歴史、我が家の対応・対策について説明していきます。
病院嫌いで困っている保護者の方の役に立てたら幸いです。
※2025年4月11日、修正及び追記しました。
長男の病院での様子
長男は身体が弱く、小さいころから今でも熱がよく出ます。
2歳くらいまでは病院に行っても、診察の時だけすごく泣いて、待合室ではニコニコしていることが多かったのですが、3歳前後から、病院に着いた時から帰り道の車の中も大泣き大暴れ。
今でも、病院の待合室では、基本ずっと泣いています。
私や祖母に密着して離れず、恐怖におびえる表情で、落ち着きたいけど落ち着けない…!って感じです。
周りに6歳で泣いている子はいないので、他のお子さんや保護者の方もチラチラ視線を感じます。

採血では、大暴れで必死に抑えても、腕を動かすので、看護師さんたちも汗だくになりながら対応…。
問診中には、先生を足蹴り、口の中を見る器具(舌圧子)を噛む、抑えつけた腕を上手にすり抜ける。
近年のコロナ検査は何度も何度も経験したので、回数を重ねるにつれて逃げ技を身につけて、顔や全身を動かして逃げようとする。
診察が終わった後もずーーーーっと待合室で泣いています。帰り道の車もまだまだ不安定。
先生や看護師さんに対して、とても申し訳なくなりますし、周りの人の目もとても気になります。
身体が大きくなった今はもう、抱っこであやすこともできないです。
このままでは親子共々疲れてしまう。なんとかしなくては・・!
まず、なぜこんなに長男は病院が嫌いなのか考えてみました。
長男が病院が嫌いな理由について
自閉症である長男が病院で暴れる理由は、以下の3つが考えられます。
- 見通しがつかない → 何をされるか分からない恐怖
- 以前の嫌な記憶から、「病院=怖い」というイメージがついている
- 触られるのが苦手(感覚過敏)
感覚過敏の詳しい症状についてはコチラの記事に書いています▼
朝から病院に行った日は、昼前には力尽きて動かなくなってしまうことも…。
それだけ長男にとって、病院がストレスであり、とても神経を使うことは間違いないです。
それでも、予防接種や発熱などの時は、病院に行かないといけません。
長男の「病院が嫌な理由」を克服するべく、私が現在までに行ってきたことは次の5つです!
親がやった5つの対策
- 暴れる長男を診てくれる病院を探した!
- できる限り大人2人で連れていく!
- 健康管理の徹底
- 絵カードなどを使って、見通しをつける
- 病院で不安を解消できるアイテムを見つける
①暴れる長男を診てくれる病院を探した!
長男がこれまで通った小児科は、6か所もあります。
現在のところに、通いだしたのは5歳の時でした。

- 先生が高齢&看護師さんが少ないので長男を押さえられない
- 長男が暴れるので、先生が必要な検査をしてくれない(できない)
- 患者さんが多く、待ち時間が長い(長男のパニックで私も待てない)
これらを理由に、5カ所の病院を変わってきました。
現在の病院に落ち着いた理由
- 待ち時間が短い
- 看護師さんの人数が多く、身体の大きな長男の対応をしてもらえる
- 長男が常に大泣きなので、待合室とは別の個室で待機させてくれる
- あの長男が点滴できた…!!
針を外せないように、しっかりと包帯でぐるぐる巻きにして固定してくれる - あの長男が採血もできた…!!
親は待合室で待ち、全て看護師さんで対応してくれる - 診察後におもちゃを無料でプレゼントしてくれる
「病院おわり」の合図になって、少しだけ恐怖の感情が落ち着くようです
この病院に出会ってから、私の「病院連れていくのが嫌だ…」という気持ちが少し軽くなりました。
②できる限り大人2人で連れていく!
我が家では、私と祖母か祖父、どちらかと一緒に行くようにしています。
長男は病院にいる限り、気持ちを切り替えることができないので、診察後すぐに祖父母に長男を預けて車まで連れて行ってもらい、私は薬の処方や支払いを済ませるようにしています。
どうしても祖父母がいない時はしょうがないのですが、そうすることで長男も私も嫌な時間を減らすことができます。
特に予防接種などあらかじめ決まっているときは、祖父母と予定を合わせていくようにしています。
③健康管理の徹底

予防接種や突然のケガなどは、予防することができません。
しかし、寒い時は暖かくさせるなどの体温調整や室温管理や歯磨き・うがいなど、なるべく病院に行かなくてもいいように、できる範囲の長男の健康管理を行なっています。
▼6歳でついに虫歯が発生。歯科受診について、コチラの記事に書いています!
④絵カードなどを使って、見通しをつける

病院に行く前に、「今から病院に行く」ということを伝えるために「病院」の写真などを見せることで、見通しをつけることです。
過去に、療育園や家の絵カードを使ってやりとりを心掛けたものの、当時の長男はあまり効果がないように感じたため断念していました。
しかし、PECSを始めたことをきっかけに、再度チャレンジしてみました。
カードを見せて「ここに行くよ」と伝えておくと、長男は、恐怖を感じて震えることもありますが、受診時に暴れることがなくなりました。
⑤病院で不安を解消できるアイテムを見つける
病院の待合室では落ち着くために、ヘッドホンをつけてYouTubeを見るようになりました。
音の鳴るもの(スマホなど)は病院では利用しにくかったりするので、ヘッドホンを着用しています。
一時的にでも、気持ちを切り替えることができ、待合室で泣かずに待てるようになりました・・・!
まとめ
長男の病院への恐怖対策として、我が家では以下の5つの工夫をしてきました。
- 暴れる長男を診てくれる病院を探した!
- できる限り大人2人で連れていく!
- 健康管理の徹底
- 絵カードなどを使って、見通しをつける
- 病院で不安を解消できるアイテムを見つける
一番暴れていた未就学児の時に、私が一番効果的だと感じた対策は「病院選び」でした。
どれだけ対策をしてもその日の気分や患者さんの多さなどにより、影響を受けてしまうので、心強い先生や看護師さんが病院にいてくれることで、親はとても安心することができます。
家庭ごとに合う方法は違いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。